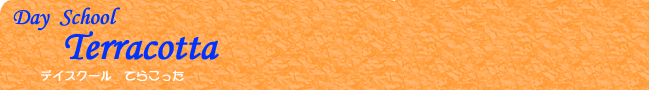|
文化とは何か。単なる芸術、美術、芸能、音楽、祭り、建築、さらには、伝統などと言うものではなさそうだ。文化とは、人のふるまいの根底にある、精神的な生きるよすが、あるいは、心の無意識裏に潜む道標、のようなものではなかろうか。
ただ単に、自分一人が俺はこうなのだ、と独自にふるまうことは、それも、たった一人の文化なのだと言ってしまえば、言えなくもないが、やはり、それは単なる個性、信条でしかあるまい。文化というものは、元来、地域社会の地域、階級社会の階級、民族、において、善くも悪くも生きる術としての、生命の糧を作り出し、生きる意味を与えるものとして、代々受け継がれてきたものではなかろうか。
その象徴としての、芸術、芸能、祭り、慣習、しきたり、伝統、なのであって、それらは、世代を越えた、人々の生活の中に受け継がれていく精神の目に見える部分と言えよう。
文化というものの根底には、宗教的、哲学的と言ってもいいような、生きていくための知恵があり、抑えきれない情念があり、限りある生命を生きる人間を見据えた中での、希望と諦観の入り混じった宇宙観が隠れている。
英語の、文化、カルチャーには、元々耕作、耕す、という意味があり、農業、アグリカルチャーとは、大地を耕す、という意味である。文化は、本来、素朴な謙虚な、人間は人間としてだけでは生きていけず、自然と共にある姿としての、敬虔な祈りを備え持った心身の営みなのである。
英太は、この五月に、村の葬儀に三回列席せねばならなかった。隣保と呼ばれる近所の十数軒で、葬式の手伝いをするというのが、この村の慣習であり、昔は、民間の葬儀場などもなく、その家で行われていたのだが、隣保の人たちが、村人のための食事を作り、道案内をし、経も読み、死者を火葬場まで運んだ。今は、ほとんどが、民間の葬祭場で葬儀を行い、隣保の仕事も、香料の受け付けぐらいになっている。このことを、古き煩わしい因習と思うか、良き温かき助け合いと見るか、で評価は変わろう。
あらゆるものが変化していくように、文化も常に変容する。外的要因がなくとも、人が新しく生まれ変わるが故に、変容し続ける。それでも、長期の閉鎖的社会においては、その変容は緩やかである。
しかし、人口の都市集中による地域の変貌、そして、科学技術の発達、生活の隅々にまで入り込んだ文明が、人々の生活を変えるように、文化も大きく変節せざるを得ない。
そこでは、もはや、地域的文化というものの持続的存続、自発的継承、自然的伝承、というものは、困難となりつつある。グローバル化した文明は、世界から地域性というものを奪い去っていく。一国内の文化さえ、単なる観光の目玉に成り下がる。
文化を守ろうとする動きも生じるが、文化を守るという言葉こそ、無理矢理の押し付けにより、伝統的文化として留めようとしている風があり、文化保護の名において、文化を陳腐なものに貶めていくことにもなり得る。
文化は、根付いてこそ意味ある文化であり、人々が実感として溶け込んでいって受け継がれるべきものであり、無理矢理根付かせ押し留めようとしても、それは、記憶と記録の発掘でしかない。
あらゆるものが変化していくのであり、当然、文化も変化していくのであって、新しい文化というものが、時々刻々、生まれていく。ただ、文明によってもたらされる文化の変容というものが、軽佻浮薄な欲望のみを助長し、人間としての孤独、社会の中の疎外に思いを致さないものだとしたら、そのような文化は、ただの流行で、次々と生まれては消えていく泡のようなものでしかない。
春霞 何ものもなく 二日月
2012年 5月25日 崎谷英文
|